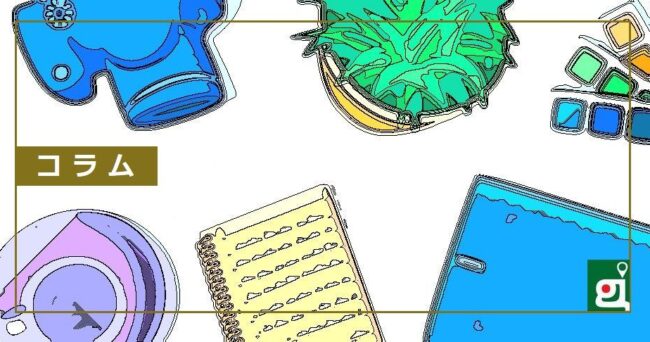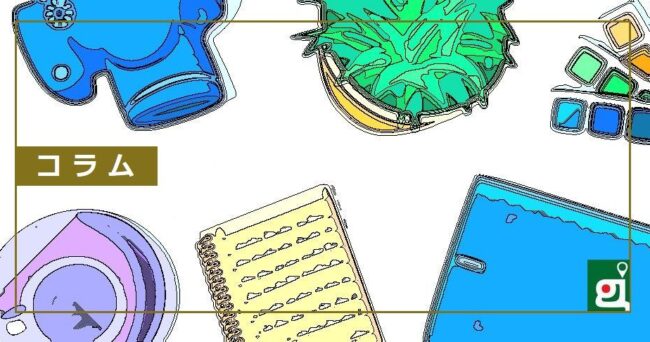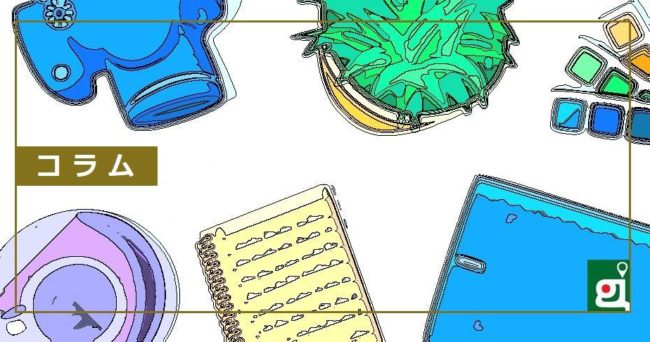アズッロ・シピオーニはどこへ
コロナで閉店に追い込まれたお店はたくさんあるが、イタリアからも悲しいニュースが届いた。映画館アズッロ・シピオーニが閉館するという。2021年3月1日付け『コッリエーレ・デラ・セーラ』紙ローマ版に掲載された記事によると、新型コロナウイルスで営業ができなくなったため、ローマ市が経済的に支援するはずだったが、行政の人事が変更されたことでうやむやになり、閉館を余儀なくされたという。
アズッロ・シピオーニはバチカン市国の最寄り駅オッタヴィアーノから徒歩2分の距離にある名画座で、1階に100席、2階に20席ほどの計2スクリーンを構え、館長シルヴァーノ・アゴスティ氏の眼鏡にかなったこだわりのラインナップが日々上映されていた。

そしてこのアゴスティというのがまた変わり者なのだ。1962年に名だたる映画人を輩出したローマの国立映画学校を首席で卒業するが、早々に大手スポンサーが介入してくる商業映画には見切りをつけて、インディペンデントで自分の納得いく映画だけを撮り続ける道を選んだ。さらに1982年には、「画家は自らの絵を展示するギャラリーを持ち、映画監督は自らの映画を上映する映画館を持つべき」という理念に基づき、映画館をつくってしまった。それがアズッロ・シピオーニだ。インディペンデントとは言え、キリスト教批判や精神医療など、社会的テーマを鋭く表現する作風でカルトな人気を誇るアゴスティの映画館は、多くのファンに親しまれてきた。巨匠ベルナルド・ベルトルッチや作曲家のエンニオ・モリコーネなど、アゴスティにシンパシーを感じる著名人も、講演を行ってきた。
僭越ながら私も折にふれ映画を観に行ったし、アゴスティにインタビューをしたこともある、いわば思い出の場所だ。大げさに言うと、アズッロ・シピオーニ閉館のニュースを聞いて、親の死に目に会えない子どもの気分になった。
閉館発表後、アゴスティはインタビューでこう語っている。「まず皆さんに安心してほしい。海水がナイフを突き刺したところで、海は死にません。文化もまた死ぬことはありません」。彼らしい前向きなコメントに、まさしくこちらも安心したが、映画館の飾りつけや看板が次々に取り払われていく映像には、やはり胸が痛んだ。
メディアでそれなりに大きく取り上げられたのがきっかけとなり、多くの人が閉館を嘆いた。だが実は、ここ数年、平常時でも映画館の営業は週末の三日間に限定される状況だった。つまり、はなから経営難だったところに、コロナでとどめを刺されたという訳だ。墓に布団は着せられず。SNS上で嘆くよりも先に行動できたことがあったはずだ。遠い異国の地から今わの際のアズッロ・シピオーニの様子を見ながら悔しい気持ちになった。
ところが話はこれで終わらない。まず閉館にさきがけて、アズッロ・シピオーニの歴史を振り返るドキュメンタリー映画をつくるというプロジェクトがクラウド・ファンディングで開始された。音頭をとったのは俳優の祖父を持つピザ職人のダニエレ・フロントーニ。ロックダウンが始まったころから、経済的に大きな打撃を受けている個人店やアーティストに連帯感を示す静かな抗議活動(protesta silenziosa)を行っており、その延長線上でアズッロ・シピオーニのドキュメンタリーを計画するにいたった。これが閉館のニュースや、それに伴うアゴスティのインタビューで注目を集め、先月末に目標額に達した。
さらに3月23日の『イル・マニフェスト』紙のインタビューでアゴスティは「市がアズッロ・シピオーニを続けるために、別の場所を提供してくれるのを、切実に待ち望んでいる」と発言している。もう何十年も空き家になっている建物なら近所にいくらでもある。文化的活動を保護するという観点に立って市が動けば、映画館の「引っ越し」が可能なのではないかと画策しているようだ。これに対してローマ市長ヴィルジニア・ラッジも自身のSNSで「アズッロ・シピオーニが継続できる方法を考えている」と前向きな発言をしている。
4月6日には芸術性の高い映画に向けられたイタリア国内の配信プラットフォームMioCinemaでアゴスティ特集が組まれるなど、閉館がきっかけとなって、アゴスティが再評価され始めている。何より御年83歳になるアゴスティのバイタリティがすごい。死に目に会えない子どもの気分と先述したが、アズッロ・シピオーニが瀕死状態から息を吹き返す可能性もまだまだあるかもしれない。
最後に手前みそではあるが、私も権利交渉などで参加している京都ドーナッツクラブという団体の働きかけで、現在、日本でもアゴスティ作品を鑑賞することができるようになった。3月末からは2か月限定で、各作品の購入ページのボーナス機能にて、アゴスティの
についてのドキュメンタリーも無料配信しているので、気になる方はまずそちらを見てほしい。日本でも、彼の映画に対する熱が少しでも伝わればうれしい。