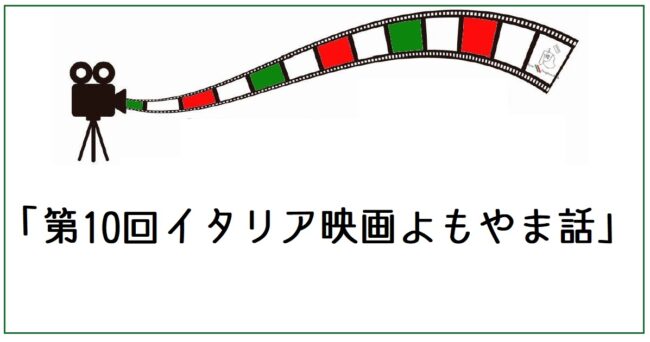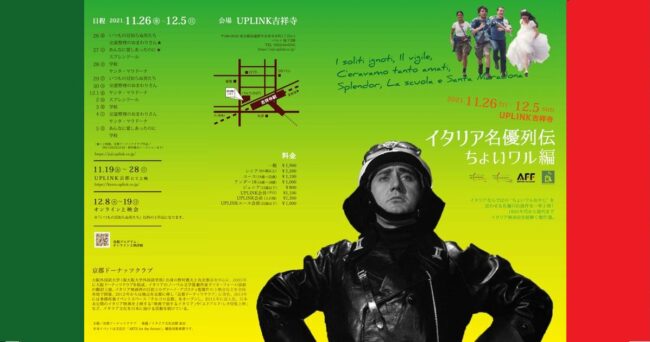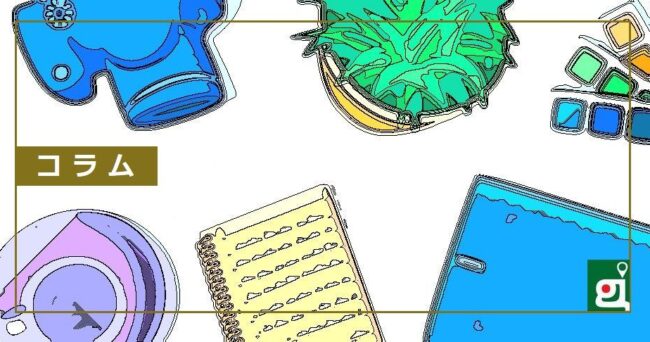「パリで中華を食べよう!」
冬のパリで、どうしても中華が食べたいという衝動におそわれた。あまりにも寒い気候のなか、体を芯から温めてくれるような辛(から)さに対する生理的欲求が生じたのだろうか。生ビールをおともにして、あっつあつの四川料理をハフハフ言いながら思うさま食べてやりたい。
パリといえば中華料理だ。というか「パリといえば○○料理だ」という文章に何を入れても成立してしまうほど、パリの食文化はじつに多岐にわたる。ヨーロッパ各国の料理をはじめ、ベトナム料理、中東料理、日本料理だって最近はばかにできないクオリティになってきた。それはそのまま、フランスがかつて世界においていかに傍若無人にふるまってきたかという歴史の裏返しでもあるのだけれど。いまではパリジャン・パリジェンヌにとって、そうした異国の料理文化はかけがえのない楽しみの一つとなっている。

なかでも中華料理は貧乏学生にとってはオアシスのような存在だった。何しろ値段がさほど高くないので、手軽にアジア料理を味わえる。日本の町中華みたいなところはそう多くはないけれど、ちょっと探せばかんたんに本場に近い味が見つかる。とても寒くて暗いある冬の夜、さいわい翌日ひとに会う用事がないことに気づいた。つまり、どれだけスパイシーなものを食べても平気ってこと。よし、ちょっと四川料理で飲んじゃいましょう!
やってきたのはサン・ラザール駅から歩いてすぐのこじんまりしたお店。お向かいには大人のおもちゃ屋さんがあるような裏通り。しかし、平日の夜でも華僑のお客さんでぎっしりになるような本気の中華である。友人たちと連れ立って攻め入ることにする。
謎の中国産ビールで乾杯したあと、メニューを眺めると目に飛び込んでくるのはトウガラシで真っ赤になった、たのもしい料理の写真の数々。麻婆豆腐やピータンを頼んだら、あとは適当に注文してみる。チャーハン頼んでしまったが、あとで聞いた話では最初からご飯ものを頼むのは中国的マナーとしては品がないそうな。
すきっ腹にピータンも麻婆豆腐もやはりうまい。なつかしの、ビールが進む味だ。ほどなくしてやってきたのは、骨付きのこまかい鶏肉をから揚げにしたものを、トウガラシと花椒などと油っぽくざっと炒めたもの。あとから調べたところによると、「辣子鶏(ラーズージー)」という料理だそうな。メニューによれば、マッシュルームやパプリカなんかを使うことでパリっぽくアレンジしているらしい。さっそく一口食べれば、たちまち舌がしびれるような嘘のない辛さ。でもしょっぱくてコクがあって、これまたビールが止まらない。
結局ほかにも頼んだりしたのだが、どれもだいたい同じ味――とはいえうまいのだが――だったように記憶している。お腹いっぱいになったところで、残った料理をみんな箱につめてもらう。翌日もこれが食べられるかと思うと嬉しいかぎりだ。みな満足して笑顔で別れ、帰途につく。この後、調子に乗ったせいでお腹を悪くしてしまうとも知らないまま。
◇ ◇ ◇
紹介したようなもののほかにも、近年のラーメンブームと肩を並べる形で「タンタンメン(nouilles Dandan)」も流行中だ。日本の某カレーチェーンのように、1から5まで辛さの段階を選べるようになっている。隣に座ったフランス人カップルが、物怖じすることなく5辛を頼んでいる姿が印象的だった。フランスでも激辛ブームが到来寸前なのかもしれない。

もちろん四川料理のほかに北京料理や東北料理も有名店はたくさんある。中華食材店にも何度となくお世話になった。おいしいお店や避けるべき食材など、書くべきことはまだまだたくさんあるのだが、この話はまたいずれ別の機会に。
また聞くところによると、中華料理のなかにもベトナム系の店か否かで味がぜんぜん違うということらしいのだが、僕の舌ではあまり違いがわからなかった。こうしてだんだん差異化しつつあるのも確かだろうが、どこの国にあっても中華料理がしっかり伝統の味を受け継いでいるのはすごいことだと思う。