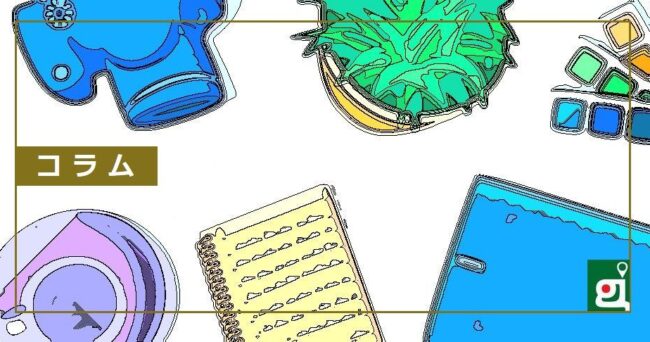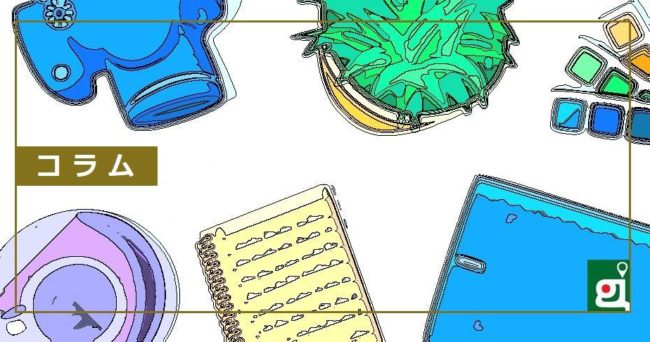秋の夜長にラテンムービー
1年間、好き放題に選曲させていただいたこの連載ですが、今回が最終回となります。
締めくくりとして、ずっと暖めていたテーマ「ラテン音楽映画」をお届けしたいと思います。ラテン音楽をよりリアルに感じていただける4本の映画を選びましたので、秋の夜長にぜひご覧ください。
まずは、ラテンドキュメンタリーの最高峰と言われている「Calle 54」(2000年)から。
こちらは、スペイン人の監督Fernando Truebaによる、世界各国のラテンジャズの巨匠13名の演奏を収めたドキュメンタリーです。
個人的な話ですが、この映画との出会いは大学時代。メキシコ人の講師が授業で観せてくれたのがこのMichel Camiloの演奏シーンでした。
天才3人が神がかった熱演を繰り広げるこの映像に衝撃を受けて以来、同作は私にとってバイブル的な存在となりました。
Tito Puente、Gato Barbieri、Chucho Valdés
、Paquito d’rivera、Jerry González…といった偉大なレジェンド達だけでなく、バックバンドにも贅沢に凄腕ミュージシャンを起用しています。その演奏シーンはいずれも「圧巻」の一言に尽きます。ラテンジャズといっても、キューバ系のPaquito d’riveraはアフロキューバンの儀式に使うバタという太鼓を、アルゼンチン人のGato Barbieriはサンポーニャやケーナを、スペイン人のChano Domínguezはフラメンコのパルマやカホンを、といった具合に各々の民族性をふんだんに盛り込んでおり、本当にどこを切り取っても飽きの来ない映画です。
ちなみに、Calle54というタイトルはNYラテン音楽の聖地と言われるマンハッタン54丁目から来ています。
次は、キューバ音楽を知る上で欠かすことのできない名作「Cuba feliz」(2000年)を紹介します。
同年に公開されたキューバ音楽のドキュメンタリー「Buena Vista Social Club」の影に隠れてしまっていますが、個人的にはこちらの作品の方がよりリアルなキューバ音楽の滋味を捉えていると思います。
主人公は、小さな体でギターを抱えてキューバ各地を旅する老齢ミュージシャン、通称”El gallo”。ギター職人や若手ラッパー、ブルースマンなど、旅先で出会う様々なアーティストとの音の交流を描いています。El galloのしわがれた歌声、砂埃の舞う田舎道、ニワトリが走り花が咲き乱れるパティオ… ありのままのキューバの生活音と風景がそこにあります。
キューバやスペインでよく知られる歌”Lagrimas negras”を女性に捧げるこのロマンティコなシーンでは、いつも涙腺が緩んでしまいます。
「語るように歌う」とはこういう事ですね。
続いて「Water Drums, an ancestral encounter」(2009年)という少しマニアックな映画を。DVDなどは出ておらず、Youtubeで正式に全編公開されています。
こちらは、ベネズエラ各地の集落に伝わる”Tambores de agua”という風習に焦点を当てたドキュメンタリー。Tambores de aguaとは、川へ洗濯に行った黒人女性たちが、歌いながら水面を叩いてアンサンブルをする遊びです。アフリカはカメルーン周辺に住むBakaという部族に全く同じ風習が残っていることから、ベネズエラ人の舞踊研究家がそのルーツを辿るべくカメルーンへ旅に出るという話です。
黒人文化のルーツを求めてアフリカに回帰するという音楽映画はたくさんありますが、ベネズエラのアフロ文化、中でも女性の風習をテーマにしたものは珍しいのではないでしょうか。
最後に、前回も少し触れましたが、Netflixで公開され世界のクンビアフリークの間で話題となった「Ya no estoy aquí」(2019年)を改めて紹介します。
舞台はメキシコのモンテレイ。コロンビアにルーツを持つために、他のメキシコ人とは少し違ったカルチャーを持つ”Cholos”と呼ばれる少年少女たちを描いた映画です。前髪を部分的に長く伸ばし、ダボっとした服に身を包み、”Cumbia rebajada”に合わせて重心低めの独特のステップで踊るのが、彼らのストリートスタイル。Cumbia rebajadaとは、コロンビアの古いクンビアの曲を、速度を落としてダブのように聴かせるモンテレイ式のDJスタイルで、この映画の影響もあり近年注目を浴びています。
この映画では、様々な場面でCumbia rebajadaのパーティシーンが登場し、モンテレイの若者の生活とクンビアとの関わりを垣間見ることができます。クンビアに関する映画自体が珍しい上に、今まであまり知られていなかったCholosのカルチャーを世界に発信したという点で、この映画は近年のラテン音楽映画の中では革新的な一本だと思います。
しかし、映画を観てると海外が恋しくなりますね。ストレスフリーに旅行できる日が早く訪れるよう願ってやみません。
それでは、またどこかでお会いできる日まで!