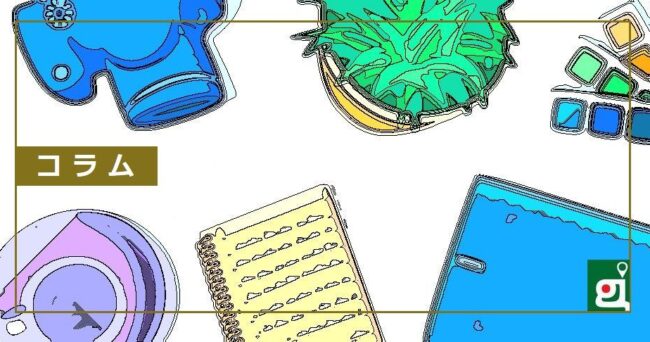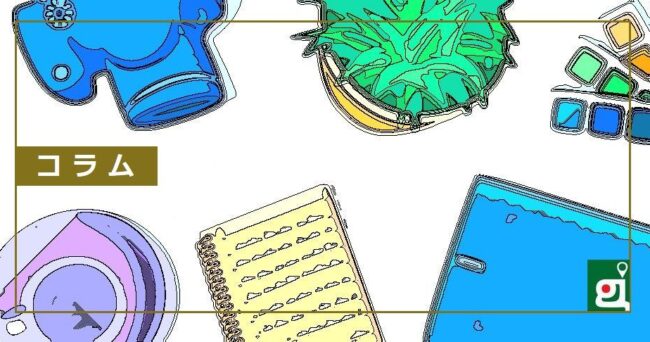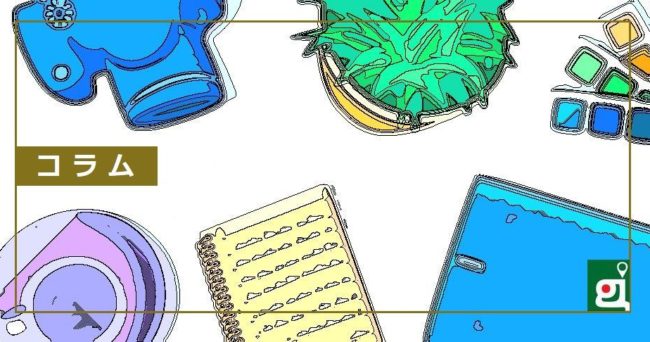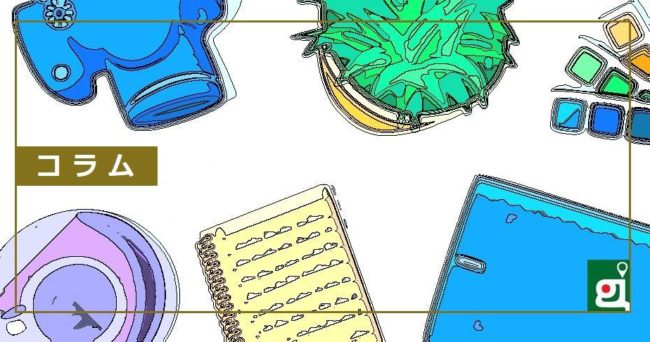「クスクスを腹いっぱい食べよう!」
渡仏したとき、いちばんに現地の友達と夕飯を食べることになった。久しぶりの再会だから「すわ、コース料理か」と意気込んでいたが、待ち合わせ場所はアルジェリア料理屋だった。クスクスを食べよう、というのだ。口にしたことはあるが、専門店でがっつり食べるのははじめて。促されるがままにクスクスと羊肉の煮込みのセットを頼んでみる。
あたりを見回すと、壁や天井の装飾はなんだかごちゃごちゃしている。けれど、不思議と異国風にまとまっている気もする。酒瓶やフライパンなんかがぶらさがっていたり、おすすめのワインがテーブルにあらかじめ置いてあったり。店内をかわいい看板ネコが闊歩している。パリの外食にしてはのどかな雰囲気だ。

運ばれてきた料理を見て、さらにその印象は強まる。繊細な料理というよりはポトフみたいな家庭料理という感じ。やや大きめの深皿の中央にでーんと煮込まれた肉が鎮座し、その周りにはニンジンやズッキーニなどの野菜がたっぷり盛られている。スープは何かのコンソメだろうか、味付けのクセはそこまで強くない。さて、それに負けないくらい大きな陶器のボウルに、たっぷりすりきりで出されるのがクスクスだ。さあさあ、アルジェリアワインと一緒にいただきましょう!
スープをかけたりしながらスプーンにたっぷりすくって食べる。いわばパンやご飯のようなものだが、それだけで食べてもじゅうぶんおいしい。ゆでたてのパスタみたいなこうばしい穀物の香り。味付けは塩とオリーブオイルに、肉を煮込んだスープをかけているような感じもある。しかし何より特徴的なのは食感だ。スプーンを入れたときは「パサパサなのかな」と思うようなさらっとした細かい粒なのだが、口に入れるとほっこりとやわらかくてとてもうまい。濃いめの味付けをしてある羊肉を一口食べたあとで口いっぱいにほおばると、もう最高だ。
友人とは久々に会うのだが会話はクスクスのことばかり。うまいうまいと言いながら茶碗二、三杯くらいの量をペロリと食べてしまっている。もうなくなったのかと思ったとたん、お代わりいる? と店長が聞いてくれる。そう、クスクスは食べ放題であるところが多いのである。そういうわけで僕らはネコに見守られながら、食後すぐ動けなくなるくらい腹いっぱい食べたのだった。
~~~~~

今では日本でも輸入食品店にも並ぶ、クスクス。もとは北アフリカの名物なのだが、移民たちによって近隣諸国へもたらされ、ヨーロッパではたくさん食べられている。かつてアルジェリアを植民地化していたフランスにもアフリカ系移民は多く、「クスクス天国」となっている。クスクスを出すお店は、イメージ的には日本でいうインド料理屋くらいある。あれ、駅前にあったっけこんな店! みたいな感じ。
上にも書いたように、クスクスは食べ放題のお店が多いので、気の置けない友人たちと腹いっぱい食べる、みたいなシチュエーションが多いようだ。店内には僕たち以外にも若そうな人たちがちらほらいたし、恰幅の良い年配のご夫婦もいたように記憶している。
これはいい、となってさっそく後日スーパーで――どこでも箱入りで安く売っている――クスクスの素を買って帰ったのだが、どう作ってもあの味にならなかった。ボイル時間、調理器具、火加減、塩味などどれかが欠けていたのだろう。結局、ご飯を炊くのがめんどくさいときの夜食として活躍することになった。クスクスにお湯を入れて三分ほど、そこへお茶漬けの素をかけて食べる「にせ茶漬け」である。今でもたまに無性に食べたくなってやってみるのだが、絶妙にひもじい味がして泣けてくる。読者のみなさんもぜひやってみてほしい。僕は責任は取りません。